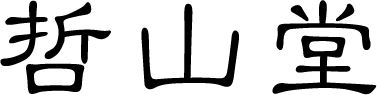偉人の意外な一面
信長には乞食を助けた逸話がある。乞食は「頑者」(かたわもの)というから身体障碍者であったろう。京へ行く街道の途次に居て、信長は通る度に気になっていたという。信長はその町の人々を集めて、「この二十反の木綿で小屋を建ててこの者が餓死せぬように面倒をみてほしい。皆がこの者に米と麦を年に二度与えてくれれば自分はうれしく思う」と頼んだ。この言葉に乞食も町の人々もみな涙を流したという。一級資料とされる「信長公記」にある話だから、実際にあったことであろう。
これは長篠の戦いに勝利して中央の支配をほぼ確立した時期である。普通なら家臣に言わせれば済む話である。あるいは、乞食にお金を渡すのが一番簡単であったろう。それをわざわざ自分が出向いて行って依頼したのか何故か?乞食にお金を渡しても、それで更生できればよいが、自堕落で浪費してしまったら援助は無駄になる。だから、乞食の自立を一番に考えたのであろう。家臣を派遣しても町の人たちが真剣に取り組んでくれるどうかはわからない。わざわざ自身が出向いて説得することで、これを信長がかなり重要視していることを認識させる意味があったのであろう。近年よく言われる自助、共助、公助に通じる考えであろう。
こうした路傍の乞食を見て心配する感性、暮らしが成り立つように配慮する計画性も凡庸な指導者の及ぶところではない。これは、町の人々が弱者を助けて共に生きて行く、という共同体の、福祉の思想であろう。信長が安土から京都への街道を整備した時も、地元の人々が共同で街道を維持、清掃盛装する体制を整えている。地域の自治の思想を信長が既に持っていた証左である。ここから弱者を町の人々がみんなで救っていくという思想も出てきたのであろう。日本の福祉史に燦然と輝く先進的な取り組みと言ってもよかろう。
こうした話に対して、これは信長の自己満足であって、支配地のすべての乞食を救ったわけではない、と批判する者もあろう。しかし、それは行動しない者の観念的な批判に過ぎない。こうした事業は、まず目の前の現実から、自分の前にいる一人から始めねばならないものなのである。
多分、こうした思想は幼少期に尾張の津島で得たのであろう。商人たちが活発に活動していた津島はそこに暮らす人々が団結して町を運営していたであろう。そうした中で、不運にも困窮してしまった町の弱者をみなで面倒を見ていたのではないか。